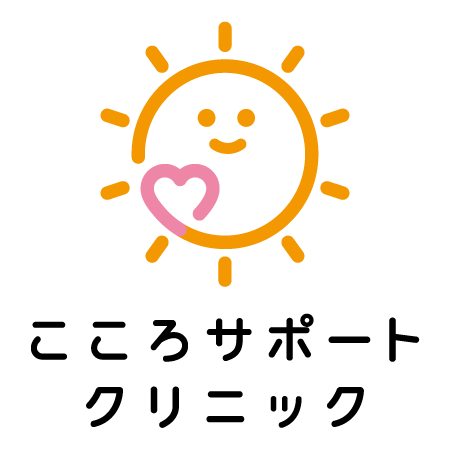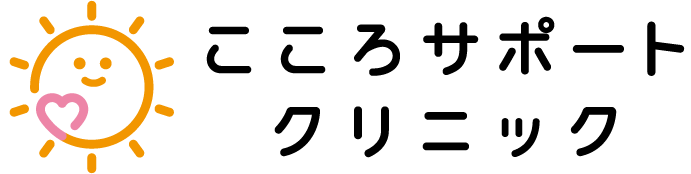不安症とは
不安症は、日常の様々な出来事について、不安や心配を慢性的に持ち続けてしまう病気です。不安や心配が過剰になりコントロール出来ず、はっきりとした理由がない事柄に対しても不安や心配が起き、それが持続してしまう状態です。また尽きることのない漠然とした不安や心配から徐々にこころとからだに症状が現れるようになり、日常生活に支障をきたしてしまいます。
不安症の原因
原因はまだ明らかにはなっていませんが、ストレス・遺伝要因・環境要因などが複雑に絡み合っていると考えられています。
不安症の症状
不安症には特徴的な症状はありません。しかしながら、自分ではコントロールできない過度な不安や心配からこころとからだに症状が現れるようになります。
| こころの症状 | からだの症状 |
| ◦些細な事でも不安になる | ◦疲れやすい |
| ◦イライラして怒りっぽい | ◦筋肉の緊張・肩こり |
| ◦集中力が落ちる | ◦もうろうとする |
| ◦眠れない など | ◦便秘や頻尿 など |
不安症の治療
不安症の治療では、まず過度な不安や心配を緩和するために薬物療法を行います。薬によって症状が落ち着いてきたら、不安や心配の症状と関連がある日常生活での悩みやストレス等への受け止め方を変化させたり、対処方法を学んだりする心理療法を行っていきます。
◦
薬物療法
持続的に現れる不安・心配に対しては、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)を中心とした抗うつ薬を用います。身体的な緊張や不眠に対しては抗不安薬や睡眠薬を用います。症状の現れ方や程度は人によって異なるため、効果と副作用のバランスを考えてそれぞれの患者さんに適したお薬を処方します。
心理療法
認知行動療法とよばれる治療法が有効とされています。認知に働きかけて、気持ちを楽にする心理療法の一つです。
物事に対する考え方・感じ方のパターンを知り、物事の捉え方を広げることでストレス耐性を上げ、ストレスに上手に対応できるこころの状態をつくっていく治療法です。状況の改善に向けて段階的な目標を作成し、それを実際に行い物事に対する考え方・感じ方、行動を変えることで日常生活での支障を減らしていくことを目指します。
よくあるご質問(Q&A)
心配性とは、もともと持っている気質のことです。几帳面すぎて細かいことが気になってしまうなど「心配しすぎる癖」であると言われることもあります。
心配性の傾向がある方でも、自分でコントロールするのが難しいような不安が原因で眠れない、仕事に集中できない、ミスが多いなど日常生活に支障をきたしている場合には心配性ではなく不安症の可能性があります。
不安症は、適切な治療や対処を行うことで症状の改善が図れます。
不安症は発病すると、うつ病・パニック症・社交不安症を併発する可能性が高くなるといわれています。いずれの疾患も当院で治療が可能です。もし気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。
不安症の方は、生活習慣を整えることで精神の安定に繋がり、結果的にイライラやネガティブな感情になることなどを軽減できます。
十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、といった生活習慣を整えるよう心掛けてみましょう。生活習慣を整えるだけでは軽減されない不安には、お薬が有効です。
不安症とは
不安症は、日常の様々な出来事について不安や心配を慢性的に持ち続けてしまう病気です。
不安や心配が過剰になりコントロール出来ず、はっきりとした理由がない事柄に対しても不安や心配が起き、それが持続してしまう状態です。
また、尽きることのない漠然とした不安や心配から徐々にこころとからだに症状が現れるようになり、日常生活に支障をきたしてしまいます。
不安症の原因
原因はまだ明らかにはなっていませんが、遺伝要因・環境要因・ストレスなどが複雑に絡み合っていると考えられています。
不安症の症状
不安症には、特徴的な症状はありません。しかしながら、自分ではコントロールできない過度な不安や心配からこころとからだに症状が現れるようになります。
。
| こころの症状 | からだの症状 |
|
|
不安症の治療
不安症の治療ではまず過度な不安や心配を緩和するために薬物療法を行います。
薬によって症状が落ち着いてきたら、不安や心配の症状と関連がある日常生活での悩みやストレス等への受け止め方を変化させたり、対処方法を学んだりする心理療法を行っていきます。
薬物療法
持続的に現れる不安・心配に対しては、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)を中心とした抗うつ薬を用います。身体的な緊張や不眠に対しては抗不安薬や睡眠薬を用います。症状の現れ方や程度は人によって異なるため、効果と副作用のバランスを考えてそれぞれの患者さんに適したお薬を処方します。
心理療法
認知行動療法とよばれる治療法が有効とされています。認知に働きかけて気持ちを楽にする心理療法の一つです。物事に対する考え方・感じ方のパターンを知り、物事の捉え方を広げることでストレス耐性を上げ、ストレスに上手に対応できるこころの状態を作っていく治療法です。
状況の改善に向けて段階的な目標を作成し、それを実際に行い、物事に対する考え方・感じ方、行動を変えることで日常生活での支障を減らしていくことを目指します。
よくあるご質問(Q&A)
心配性とは、もともと持っている気質のことです。几帳面すぎて細かいことが気になってしまうなど「心配しすぎる癖」であると言われることもあります。
心配性の傾向がある方でも、自分でコントロールするのが難しいような不安が原因で眠れない、仕事に集中できない、ミスが多いなど日常生活に支障をきたしている場合には心配性ではなく不安症の可能性があります。
不安症は、適切な治療や対処を行うことで症状の改善が図れます。
不安症は発病すると、うつ病・パニック症・社交不安症を併発する可能性が高くなるといわれています。いずれの疾患も当院で治療が可能です。もし気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。
不安症の方は、生活習慣を整えることで精神の安定に繋がり、結果的にイライラやネガティブな感情になることなどを軽減できます。
十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、といった生活習慣を整えるよう心掛けてみましょう。生活習慣を整えるだけでは軽減されない不安には、お薬が有効です。